 とある女性
とある女性よく考えたら、浮気ってなぜダメなんだろ、、、?



今回は、社会、心理、生物の3視点から考察してみよう!
現代では、「浮気は倫理的に良くない事」というのが当たり前になっています。しかし、感情論を抜きにすると浮気がなぜダメなのかについては、納得のいく説明がなされることはありほとんどありません。
ですから、浮気はなぜダメなのかについての理由が、気になりますよね?結論、あくまでも社会、心理、生物的側面から見ると浮気がなぜダメかの理由は、それぞれ以下のようになります。
浮気はなぜダメなのかについての理由
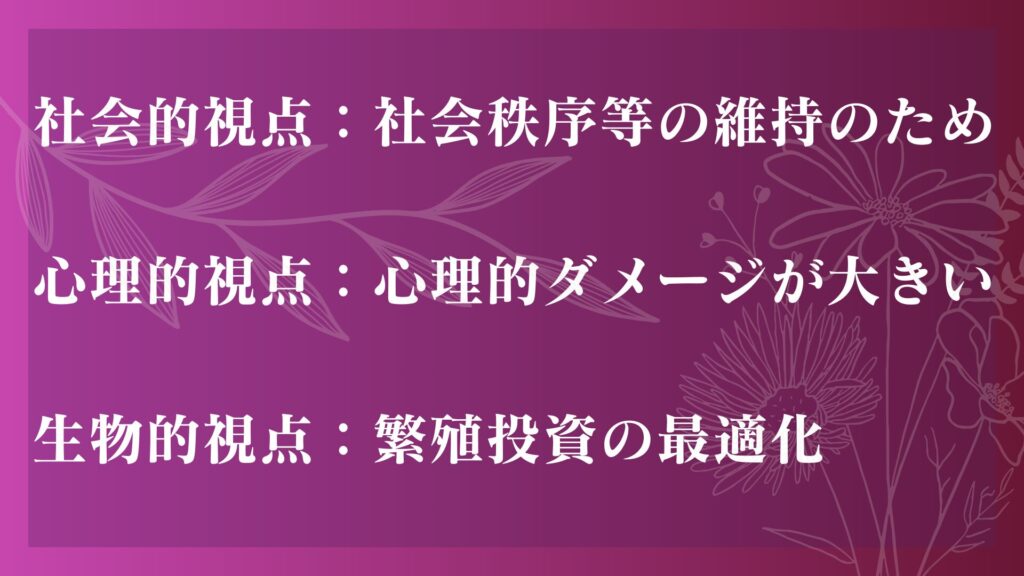
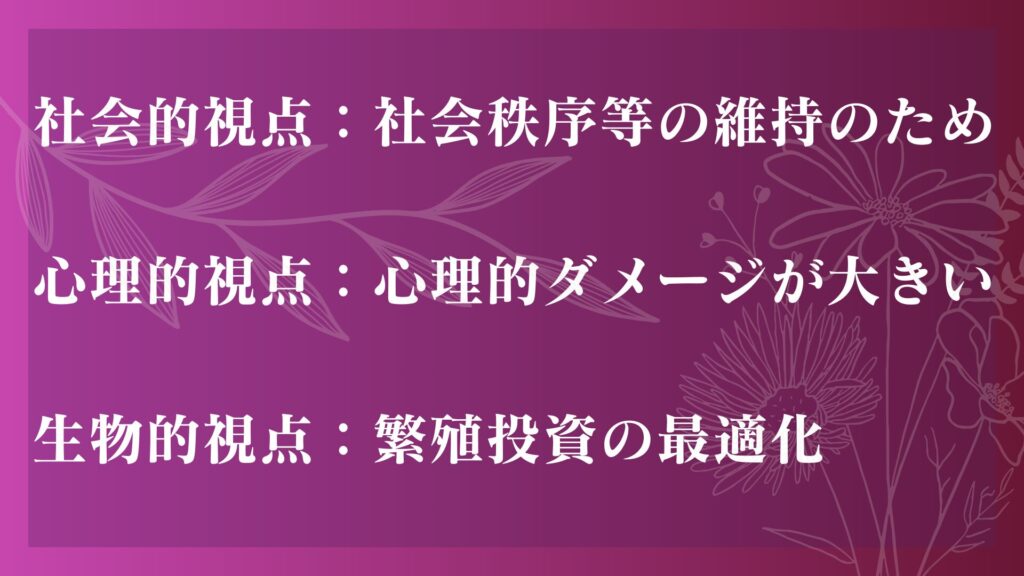



浮気禁止の風潮は、社会秩序等の側面が一番大きいね。
浮気が良くないとされるのは、主に社会維持のためからの側面が大きいですが、心理ダメージも軽視はできません。実際、パートナーに浮気されたり浮気疑惑が発生したら、怒りや悲しみといった様々なネガティブ感情で心中穏やかでいられませんよね?
もし、パートナーの浮気疑惑の真相を突き止め適切な対応を取りたければ、確かな腕を持つ探偵に依頼して調査してもらうのがベストです。自分で調査するのもある程度は可能ですが、バレた時のリスクが高すぎるのであまりお勧めできません。
厳しい審査をクリアした優良探偵社と提携する街角探偵相談所なら、あなたに最適の探偵社を格安で紹介してくれるので安心です。浮気疑惑の真相を確かめ心穏やかな日々を取り戻すため早急に対策したい方は、ぜひ街角探偵相談所の公式ページから、無料相談を申し込んでみて下さいね!
╲提携探偵社はえりすぐりの全国100社以上╱
╱相談・面談・紹介は無料╲
浮気はなぜダメとされるのかを3つの視点から徹底解剖
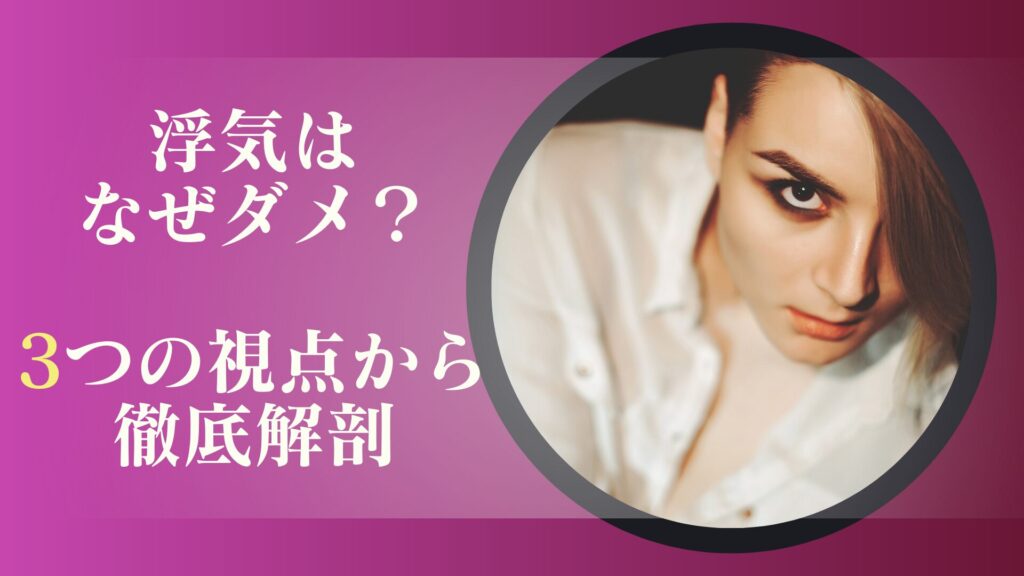
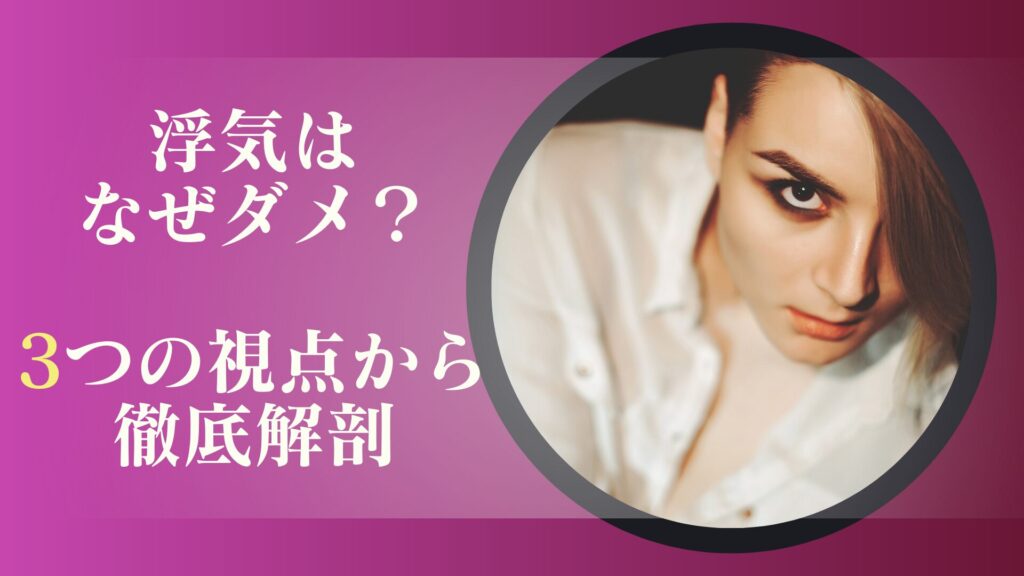



浮気はなぜダメとされるているんだろうか、、?



では、3つの視点から徹底的に分析してみよう!
まずは、浮気がなぜダメとされるのかについて、社会、心理、生物の3つの視点からそれぞれ分析していきたいと思います。
冒頭でも紹介したように浮気がなぜダメとされるのかを、それぞれの視点から考えた結果は、大まかに以下の通りです。
浮気はなぜダメとされるのか分析する視点
- 社会的視点:社会秩序等の維持のため
- 心理的視点:心理的ダメージが大きい
- 生物的視点:繁殖投資の最適化



それぞれ、くわしくみていこう!
社会的視点:社会秩序等の維持のため
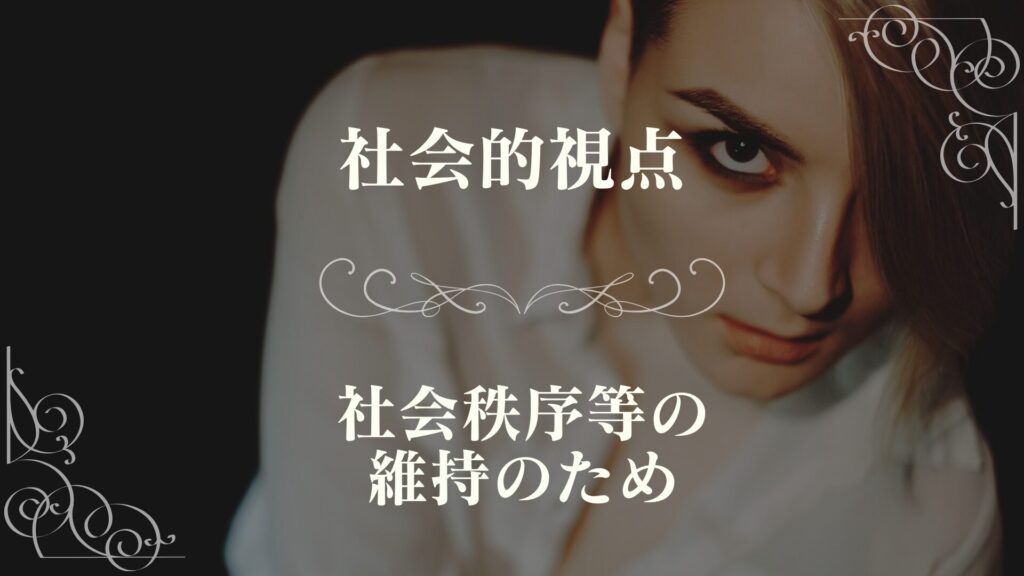
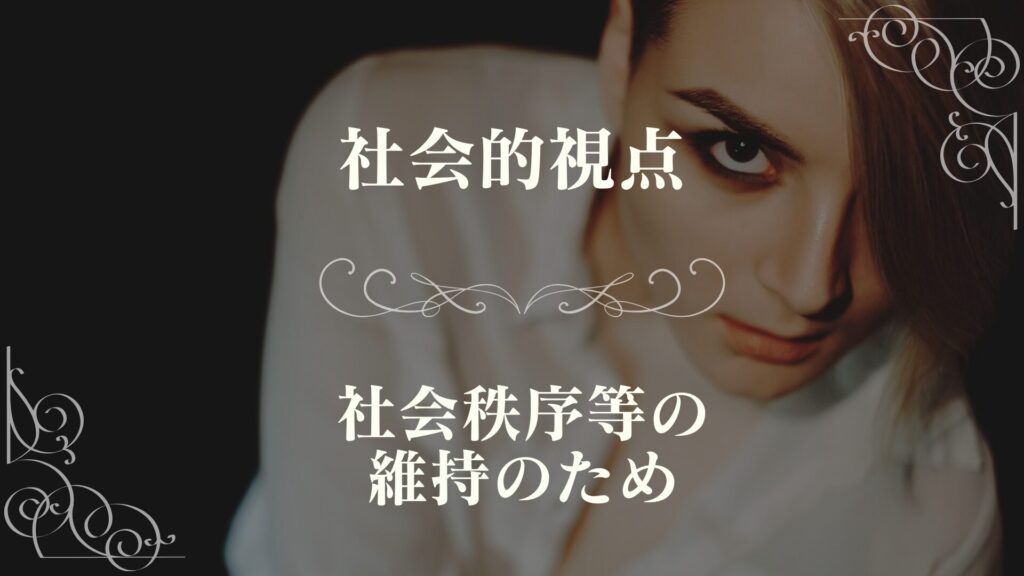
浮気がなぜダメかを社会的な視点から考えた場合、浮気は社会秩序等の維持のためにダメとされていると解することができます。
今日では多くの国々で一夫一妻制が採用されていますが、これは家族の安定や社会秩序の維持に寄与する婚姻形態であるといえましょう。



まあ、現在では一夫一妻制が普通よね。
一夫一妻制は、配偶者間の信頼を基盤に、子どもたちに安定した養育環境を提供し、財産や権利の継承を明確化することで、社会全体の効率性を高める役割を果たすものです。
参考:Anatomy of Love: A Natural History of Mating, Marriage, and Why We Stray
事実、日本の法条文には、複雑な家庭関係や相続問題を防ぎ安定した社会秩序を確保しようとする意図が明確に見て取れます。
参考
ちなみに、個人の幸福感という観点からみると、必ずしも一夫一妻制が最適解とは言えないとする見方もあるようです。
「補足」現代における一夫多妻制の現状と女性の幸福度について
2025年現在、一夫多妻制を法的に認めている国は主にイスラム教徒が多数を占める国々(特に中東やアフリカの一部の国々が該当)である。
これらの国々では、宗教的および文化的な背景から一夫多妻制が許容されている。
なお、カナダのゲルフ大学による研究では、一夫一妻制の夫婦とオープンリレーションシップ(互いの了承のもとで他のパートナーとの関係を持つ)の夫婦を比較した結果、幸福度に大きな差は見られなかったと報告されている。
参考
Open Relationships Just as Satisfying as Monogamous Ones, U of G Study Reveals
ただし、このような傾向は、すでに一夫一婦制に最適化された多くの国々でも通用するとは中々いいがたいので、慎重に受け止めるべきである。
心理的視点:心理的ダメージが大きい
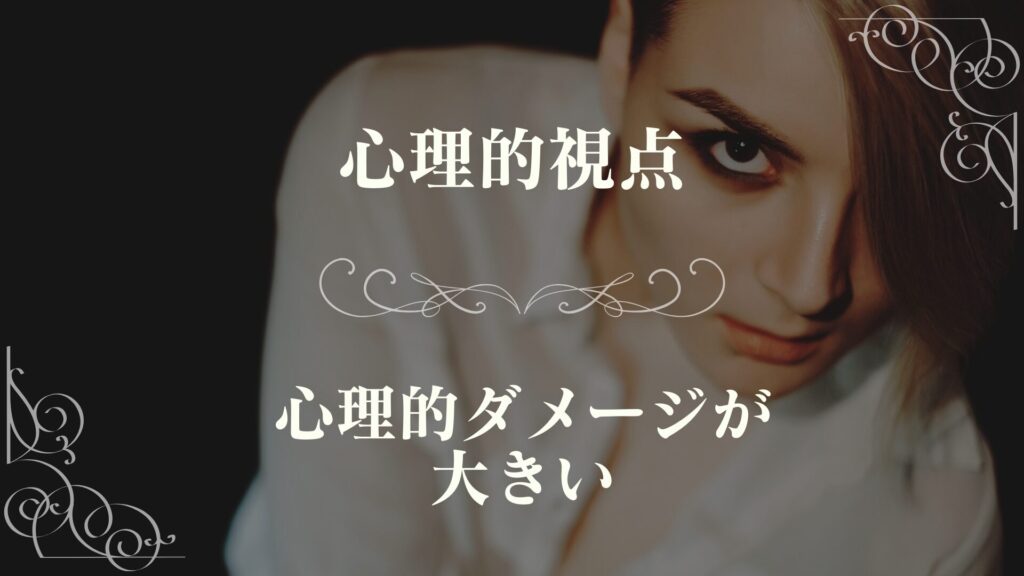
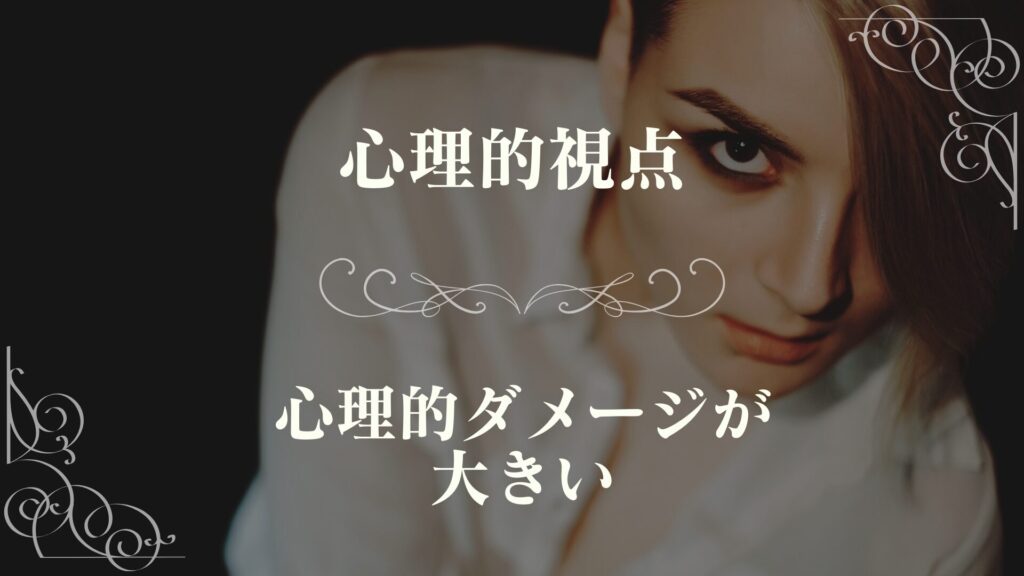
浮気がなぜダメかを心理的な視点から考えた場合、浮気はパートナーに対する心理的ダメージ非常に大きいためにダメとされていると解することができます。
事実、浮気をされた人には以下のような心理的ダメージが発生するといわれています。
浮気されることで発生する心理的ダメージの具体例等
- 裏切られた感情
- 自己肯定感の低下
- 不安と疑念の増加
- 孤独感の増加
- 怒りと憎しみの発生
- トラウマの形成
- 罪悪感
- 恥の感覚
浮気によって、上記のように様々な心理面でのデメリットが発生するので、「浮気はよくない!」といわれるのも非常に妥当な話といえます。
上記のような、デメリットが生じる背景に関して様々な説明が可能ですが、その中で最もわかりやすいものは、「パートナーの存在が自分のアイデンティティーの一部となっているから」というものでしょうか。



ん?アイデンティティーの一部??
パートナーとの間に一定以上の信頼関係が構築されている場合、パートナーの存在は「自己概念を形成する一つの重要要素」となっているので、浮気は「自己崩壊」単なる裏切り以上の意味を持ちます。
自己概念の崩壊は、自分自身の存在意義にまで影響を及ぼす深刻な問題なので、そこからの立ち直りには自己概念の再構築が必須となりかなり労力を要するものです。
生物的視点:繁殖投資の最適化
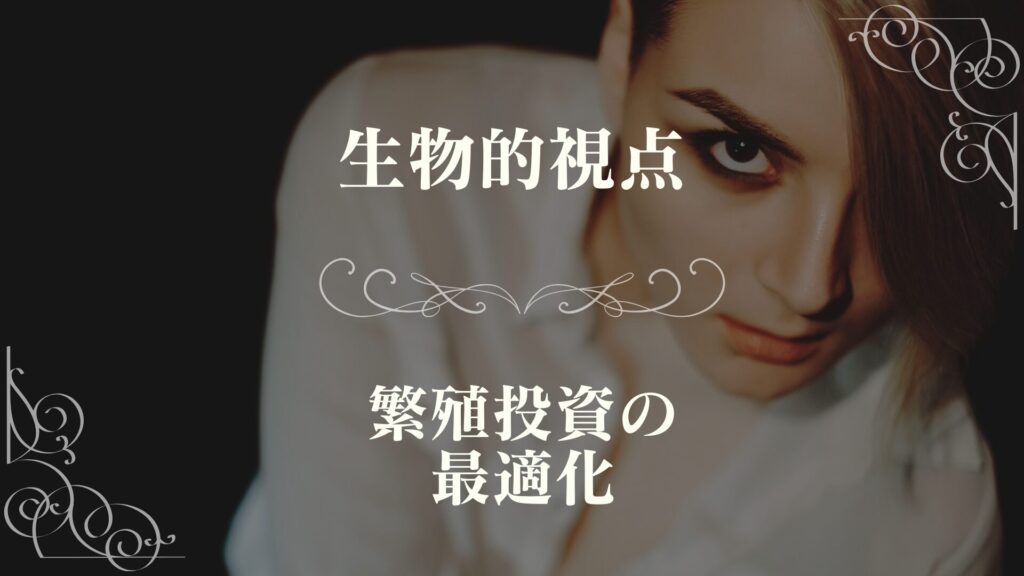
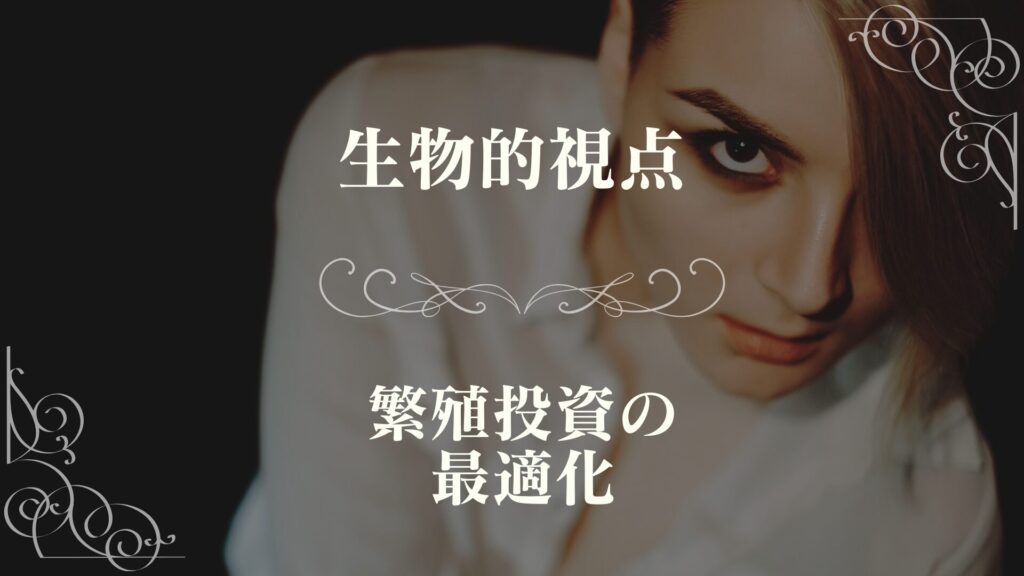
浮気がなぜダメかを生物的な視点から考えた場合、浮気がダメなのは繁殖投資の最適化の結果と考えることもできます。
浮気を禁止し一夫一婦制を採用することで、以下のようなメリットが得られます。
一夫一婦制を採用することで得られるメリットの例
- 協力して子育てする事で子供の生存可能性が向上する
- 遺伝的投資が保証される(例:托卵の防止)
- パートナー間で資源(食料、住居、保護など)を効率的に共有できる
- 競争の抑制による社会的安定性の確保(主に男性の競争の話)
- 性病の拡散リスクの低減
- 性淘汰の均衡化による遺伝的多様性の増加
上記のように、一夫一婦制を採用することで得られるメリットには、様々なものがありますが、これらは「遺伝的多様性の確保」と「子供の生存確率の向上」、「男性の過剰競争の抑制による社会的安定性の確保」の3つに大別できます。
特に生物学的な文脈では、遺伝的多様性の確保が一番重要でしょう。なにせ、様々な遺伝形質を持つ個体がいる事で、大きな環境変化が起こっても種が絶滅しなくて済むのですから。



ん?なんか、めんどくさい話になってきたなあ、、。
ここで、遺伝的多様性の話をされても、「はて?」と思われる方もたくさんいると思うので、少し具体的に考えてみましょう。
例えば、一夫一婦制が採用され重婚が禁止される事で、いわゆるモテる強者男性の異性総取りが抑制され、いわゆる非モテ男性が実子を持てる可能性が出てきます。
いつの世も、モテる男性は極めて少数派である傾向にある
女性としては、「若くてイケメンで有能で資産家」等といった男性の方が、子も優秀な美形になり生存可能性が高くなるので、結婚相手としては望ましいはずです。
しかし、こうした男性だけが次世代に子を残すことになると、全ての次世代が似たような性格特性や容姿、能力を持った人ばかりになってしまい多様性に欠けてしまいます。



そう?非モテなんて、いなくなっていい気がするけど、、。
人によっては、「非モテ男性なんてキモいから根絶されてよくない?」みたいな感想を持つかもしれませんが、必ずしもそうとは言えません。
例えば、モテる男性ほど自己中で外向的な傾向がある一方、非モテ男性ほど協調的で内向的性格をしています。そのため、世の中の男性が前者だけで構成されたら以下のようなトラブル等が頻発するかもしれません。
- 外向的な人が多くなるために感染症の拡散が早くなる
- 血の気の多い人間が増えて暴力系犯罪が増える
- 精密な作業が苦手な人が増え技術の発展が遅くなる
- リスクの多い決定をする人が多くなり社会が滅亡する可能性が高くなる
社会は様々な特性を持った人がいるおかげでうまく回っているので、いわゆる非モテ傾向の強い男性もいなくては困るわけです。
そのため、ほとんどの人が家庭を持つことのできた昭和時代のいわゆるお見合い結婚は、社会の維持や遺伝的多様性の確保の点で、かなり優秀な慣習だったのかもしれません。
「補足」遺伝的多様性の確保についてのもう少し突っ込んだ話
人類を含む哺乳類は、これまで有性生殖によって、環境変化による種の絶滅を防止するために遺伝的多様性を確保してきたとされている。
ただ、有性生殖の利点については諸説あり、以前の外的な環境変化への対応のために遺伝的多様性を確保したとする説では、有性生殖程度では急激な環境変化に対応できないとされ、現在では否定される向きにある。
現状、有性生殖の利点は、赤の女王仮説から語られる傾向が強い。
赤の女王仮説(Red Queen Hypothesis)とは、生物が進化し続けなければ環境に適応できず、生存競争に敗れるという進化論の仮説であり、この名前は、ルイス・キャロルの『鏡の国のアリス』に登場する赤の女王の「同じ場所にとどまるためには全力で走り続けなければならない」というセリフに由来している。
特に人類の場合、この赤の女王仮説の文脈では病原体と宿主の関係性が強調されるため、人類は自身に寄生する可能性があるウィルスや細菌らの変異に対応するために有性生殖が役立つとされている
浮気はなぜダメかについての一般的見解17選





浮気はなぜダメかについての一般的見解には、どんなものがある?



大体、代表的なものは以下の17個かな。
次は、浮気はなぜダメかについての一般的見解について、ざっと見ていきたいと思います。ネットを精査する限り、浮気はなぜダメかについての一般的見解には、以下のようなものがあるようです。
浮気はなぜダメかについての一般的見解17選
- 信頼を裏切る行為だから
- 感情的な傷を与えるから
- 関係が不安定になるから
- 一度失った信頼は取り戻せないことが多いから
- 精神的な負担を増すから
- 裏切られた感情が強くなるから
- 関係が終わるリスクが高いから
- 自己肯定感が低くなるから
- 倫理的に問題があるから
- 浮気によって家庭が壊れることがあるから
- 親密な関係が損なわれるから
- 嘘をつくことになるから
- 浮気相手に対する責任が発生するから
- 周囲の人に悪影響を及ぼすから
- 浮気相手との関係が続かないことが多いから
- 浮気によって後悔することが多いから
- 浮気が繰り返されるリスクがあるから
上記を見ると、当たり前ではありますが、感情的な側面からの理由が多いですよね。



まあ、そりゃねえ、、誰も生物的な視点から浮気を非難しないって。
ちなみに、上記浮気はなぜダメかについての一般的見解の内で、一番多かったと思われるものは「親密な関係が損なわれるから」です。
やはり、浮気は、「信頼関係への裏切り」ととらえられる向きが強いようですね。
浮気がなぜダメかわからない人にありがちな3つの心理特性
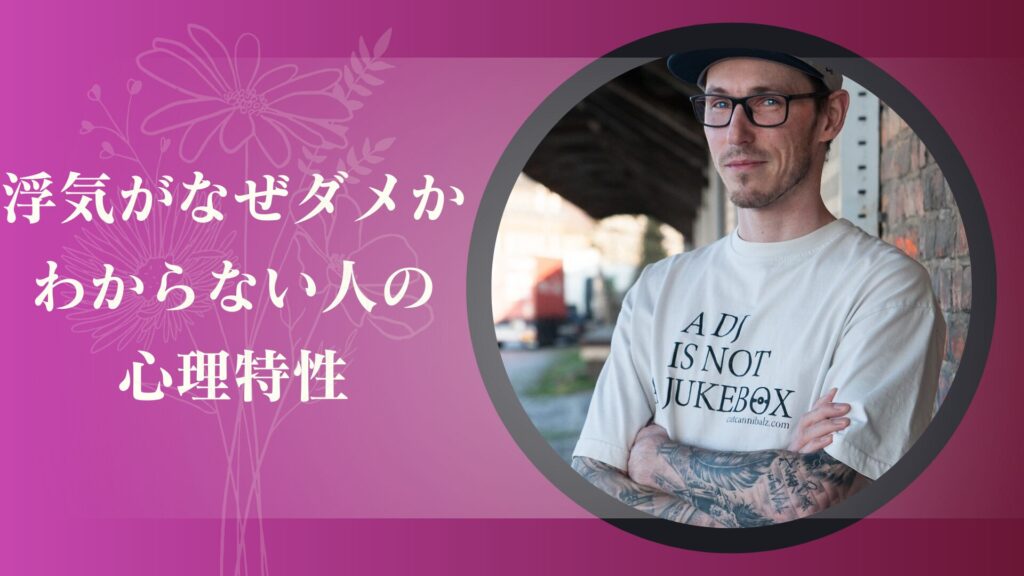
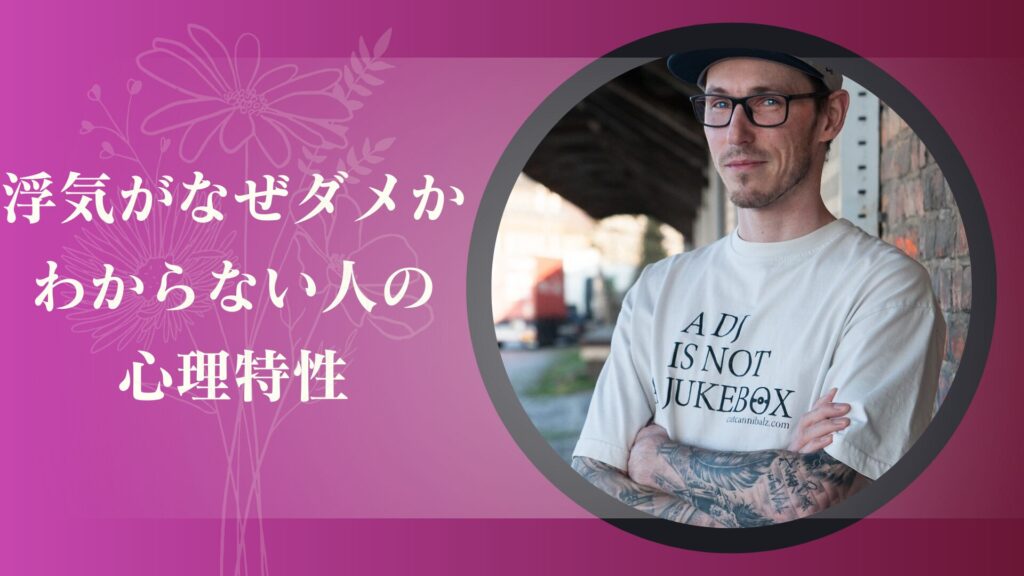



浮気がなぜダメかわからない人の心理特性には、どんなものがあるの?



3つあるね。
浮気はよくないと認識しているのが普通ですが、浮気がなぜダメかわからない人もそれなりにいるものです。常識人にとっては、ちょっと意味が分かりませんよね。
そこで、浮気がなぜダメかわからない人の心理特性について、具体的に見ていきたいと思います。浮気がなぜダメかわからない人の心理特性の内、代表的なものは以下の3つがあります。
浮気がなぜダメかわからない人にありがちな3つの心理特性
- 心理特性①:共感性が低い
- 心理特性②:浮気をステータスと思っている
- 心理特性③:貞操観念が壊れている



それぞれ、詳しく見ていこう!
心理特性①:共感性が低い


浮気がなぜダメかわからない人の心理特性の1つには、共感性が低いというものがあります。
共感性が低い人、具体的にはサイコパスや極度のナルシスト(自己愛性パーソナリティー障害含む)、マキャベリストといった人たちは、浮気がなぜダメかを理解はできてもわかりません。



理解してもわからない、、、?どゆこと?
なお、ここでいう「理解はできてもわからない」とは、端的に言えば「理屈としてなぜダメかはわかるが罪悪感がないので感情的に共感できない」という事です。
特に、上記のサイコパスや極度のナルシスト(自己愛性パーソナリティー障害含む)、マキャベリストといった心理特性を持つ人は、単なる自己中以上に他人を道具のようにしか考えないので相当にたちが悪く、浮気を平然と行う傾向にあります。
「補足」サイコパスや極度のナルシスト、マキャベリストの他人を道具として扱う思考について
サイコパスや極度のナルシスト、マキャベリストと呼ばれる人たちは、以下のような思考・行動をとる傾向にある。
- 他人は「対等な存在」ではなく、「使うための道具」
- 相手の気持ちは気にしない、または理解できない
- 自分のためなら平気でウソや操作をする
- 他人を支配したがる
彼らは上記にある通り、「他者を対等な存在とは思っていない」という点が非常に共通しており、他人を自身の目的を達するための道具として認識している。彼らは上記にある通り、「他者を対等な存在とは思っていない」という点が非常に共通しており、他人を自身の目的を達するための道具として認識している。
ただ、マキャベリストに関しては、浮気を単なる性欲発散や寂しさの穴埋めをするための行動ではなく「罪悪感を植え付け支配する手段」や「弱みを握るための手段」などど解釈していることもまま見受けられる点が特徴的である。
浮気がなぜダメかわからない人の心理特性の1つに、共感性が低い事がある
心理特性②:浮気をステータスと思っている
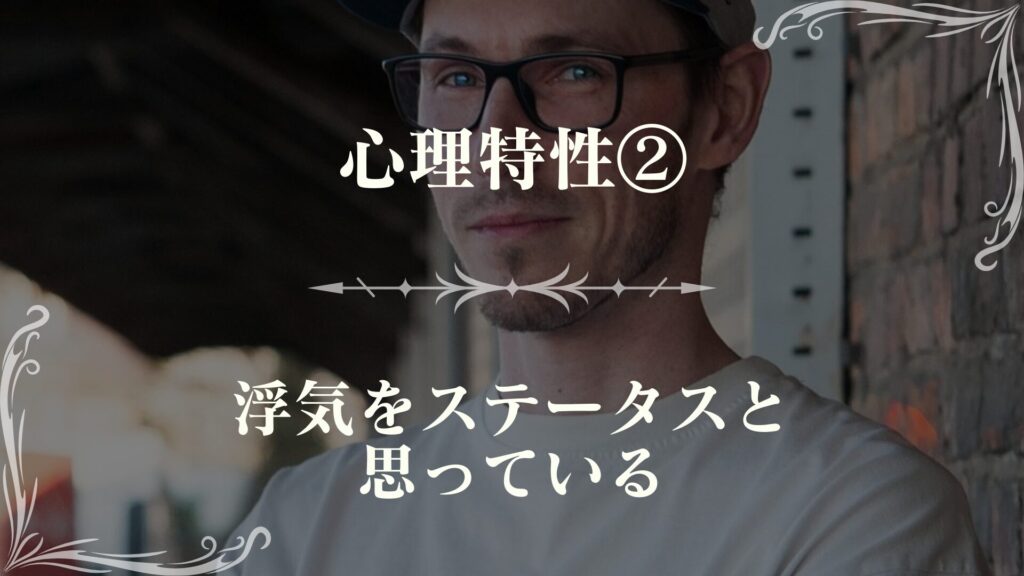
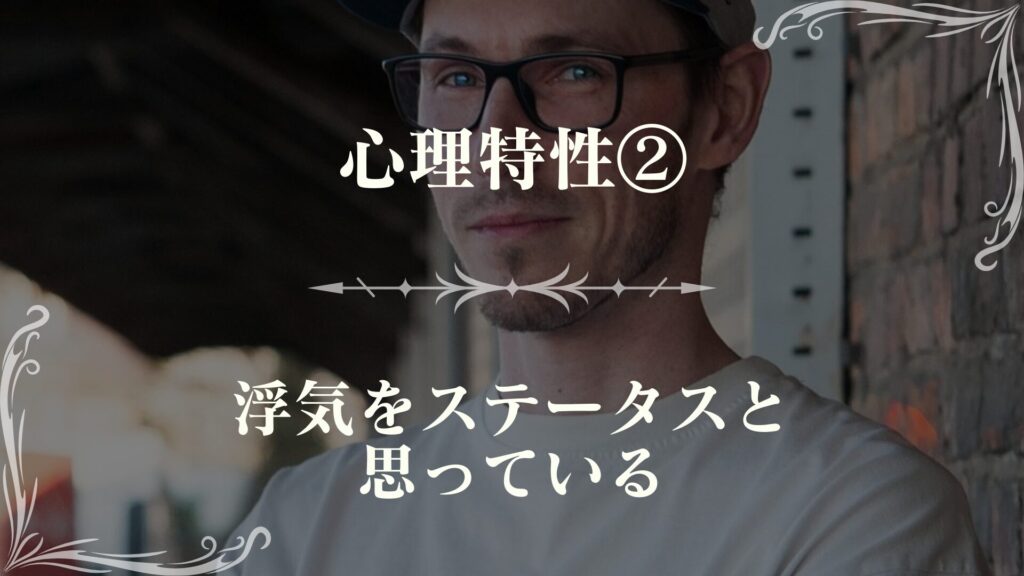
浮気がなぜダメかわからない人の心理特性の1つには、浮気をステータスと思っているというものがあります。
ただ人によっては、なぜ浮気をステータスなどと考えられるのかと不思議に思う方もいるかもしれません。特に、女性は意味が分からないかと思います。



確かに、浮気がステータスなんて謎よね。
浮気をステータスと感じる人は、端的に言えば「浮気=自分の魅力の証明」と解釈しているから、浮気する事をステータスだと思っているのです。
おそらく、この感覚は女性からしたら「はて?」という感じかもしれませんが、実は、これには男性と女性のモテやすさなどの違いに由来するところが大きいです。
「補足」男性の場合、浮気がステータスになりやすい理由
一般に、男性の方が女性に比べて、浮気をステータスと認識している傾向が明らかに高い。
この背景には、生来的に設定されている男女間でのモテ格差の存在があると考えられる。これは具体的には、女性の方が男性に比べて圧倒的にモテやすい傾向にあるという事を意味している。
男性は通常、女性に比べ圧倒的にモテないために、モテる(性行為できること)男性は非常に希少であるが、女性は何をせずとも女性というだけで言い寄られることが多い(いわゆる穴モテの事)くらいにはモテるのが当たり前である。
言ってしまえば、男性はモテるために努力が必要であるが、女性はモテることに努力が要らないとすらいえる。
あくまでも生物的な文脈では、「子孫を残す機会に恵まれる事を志向する」のが本能であるため、男性の本能にとってモテる事の価値は非常に高いものとして認識される傾向にある。
そういった事情もあって、男性の場合はモテる事、つまり浮気をしようとすればできる事や経験人数といったものが自身の優秀さの証明という認識につながりやすいのである。
一方で、女性の場合は、そもそもがモテる状態なので、女性のいわゆる経験人数の多さは「節操のなさや軽薄さの証明」や「恥の数」とすらいってもいいものかもしれない(一般に女性が自身の経験人数を正直に言う事について後ろめたさを感じる傾向にあるのは、本能的にこれを自覚しているからとも考えられる)。
ただ男女いずれの場合であれ現代社会においては、浮気は節操のなさや軽薄さの証明という認識をされるのが一般的であり、浮気がステータスになることはまずありえない。
浮気がなぜダメかわからない人の心理特性の1つに、浮気をステータスと思っている事がある
心理特性③:貞操観念が壊れている
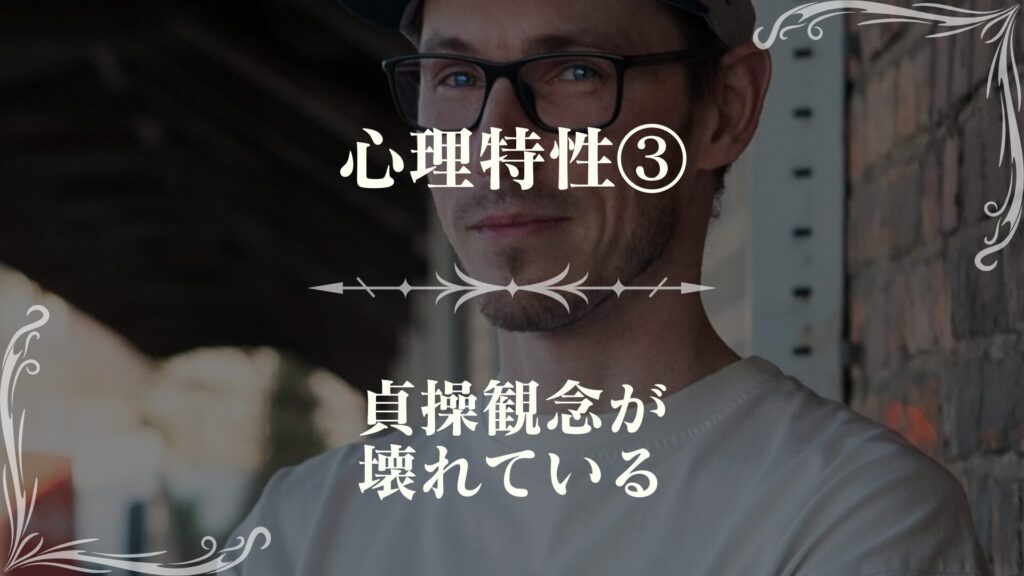
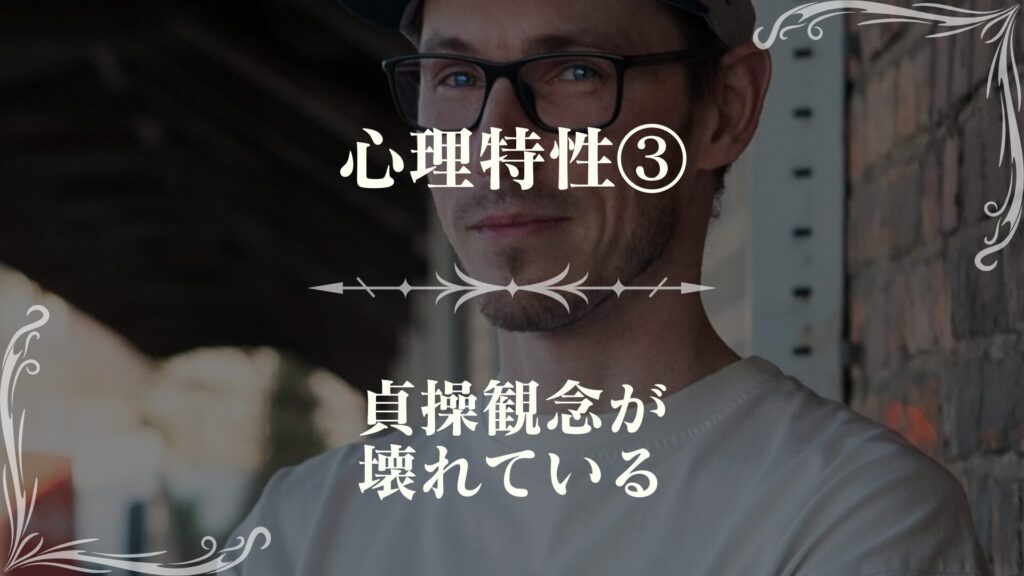
浮気がなぜダメかわからない人の心理特性の1つには、貞操観念が壊れているというものがあります。
当然といえば当然ですが、貞操観念が破綻している人は、当たり前のように浮気をしますし、浮気した事実に対して罪悪感を感じる事も基本的にありません。そのため、更生する可能性は、サイコパスなどよりはましですが低い傾向にあります。



まあそりゃあねえ、そもそも悪い事してる自覚ないんだもんね。
なお、貞操観念が壊れている原因については、以下のようなものが考えられます。
貞操観念が壊れている原因の具体例
- 愛着形成上の問題(例:自分が性的に求められることでしか価値を感じられない)
- 家庭の性的価値観の影響(厳しく抑圧されて育ったため、大人になってから反動で奔放になる)
- 親の不貞や家庭内の不安定さ(両親の浮気や不安定な家庭環境での生育を経て、「誠実な関係は無意味」との認識が深まる)
- 周囲の環境の影響(交友関係や職場環境が性的に奔放な文化を持つ)
- 衝動性・快楽主義的傾向が強い(サイコパスなど)
上記のように、貞操観念が壊れてしまう原因については、非常に様々なものがあり一様ではありません。またこれら要素の内の複数が相互に影響を与え合って、貞操観念の崩壊を後押ししている傾向にあります。
ただ、個人的に最もよく観察されるのは、やはり何といっても生育環境などに恵まれなかったせいなどで愛着形成不全を起こし、それが主なトリガーとなって貞操観念が崩壊するパターンでしょうか。
浮気がなぜダメかわからない人の心理特性の1つに、貞操観念が壊れている事がある
浮気をなぜダメと感じるかを心理学的にさらに深く分析





私たちは、浮気をなぜダメと感じるんだろうね?



では、心理的側面から少し突っ込んで考えていこう!
先ほど、浮気がなぜダメとされているのかを心理的ダメージの大きさの観点から述べましたが、ここでは浮気をなぜダメと感じるかについて心理学的な側面からさらに詳細に分析していきたいと思います。
浮気をダメと感じる心理学的文脈からの理由は、以下の通りです。
浮気をダメと感じる心理学的文脈からの理由
- 理由①:愛着の安全性
- 理由②:本能的な忌避感
- 理由③:認知的不協和
- 理由④:自己肯定感とアイデンティティの喪失



それぞれ、詳しく見ていこう!
理由①:愛着の安全性
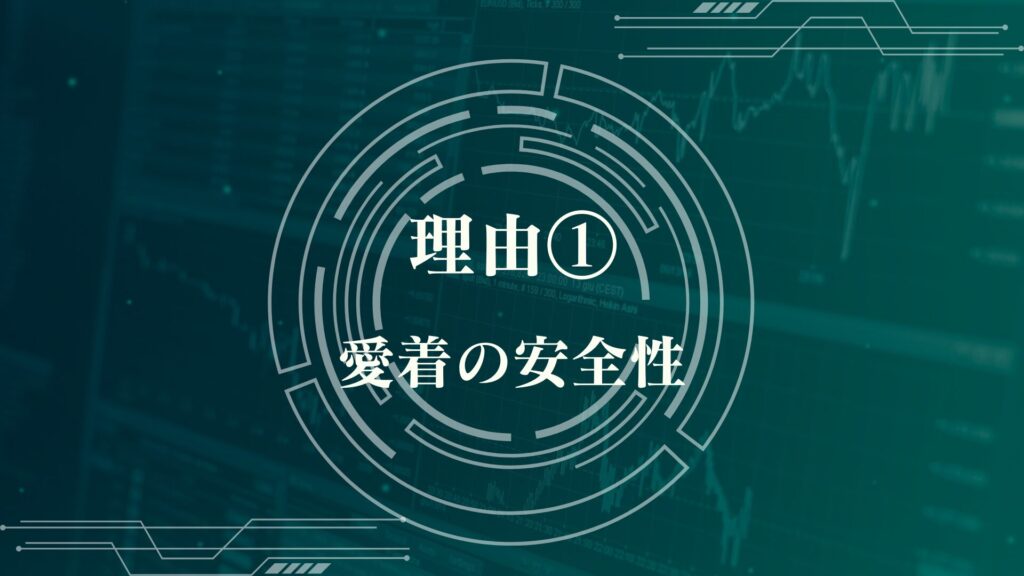
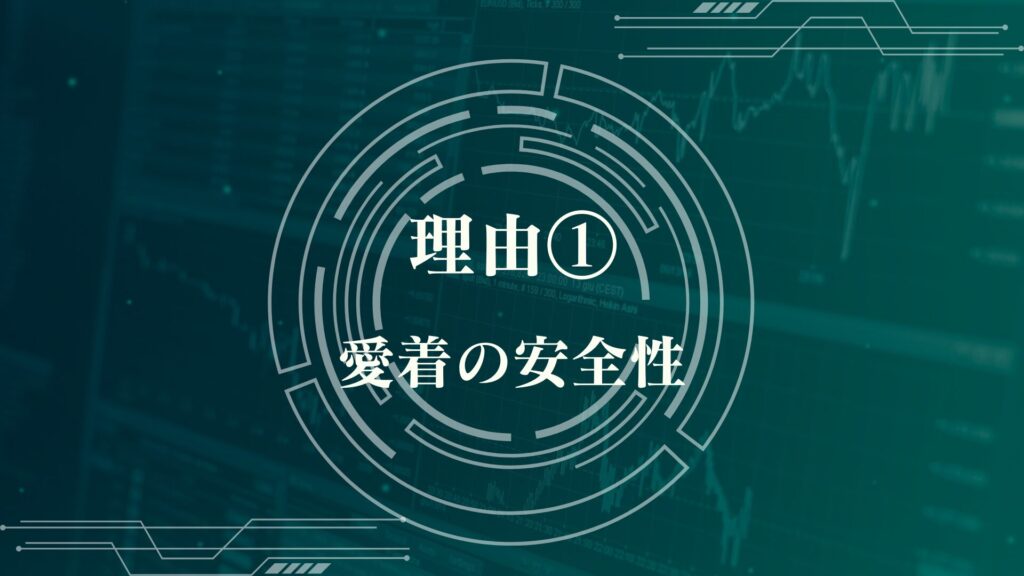
私たちが浮気をなぜダメと感じるかは、愛着の安全性の観点から考えられます。
人間には、「安定した愛着を求める本能」と「愛着の独占欲」の2つが備わっていると考えられているので、それらを侵害する浮気に対して忌避感を感じるのは当然の流れといえるでしょう。



安定した愛着を求める本能と、愛着の独占欲?
安定した愛着を求める本能は、 浮気によって「相手が自分から離れるかもしれない」という不安を感じ心理的安全が脅かされるため、不快感や恐怖を覚えることになります。
そして、愛着の独占欲に関しては、「パートナーが自分だけを大切にしてくれる」という信念が前提にあるので、それが裏切られると強いストレスを感じる事になるといえるのです。
「補足」愛着スタイルとは?
愛着スタイル(Attachment Styles)とは、幼少期の親との関係が基盤となって、成人期の対人関係や恋愛に影響を与える心理的パターンの事である。
愛着スタイルは、心理学者のメアリーエインズワースによる「ストレンジ・シチュエーション実験」によって、幼児の愛着スタイルを以下の3つに分類されている(のちに4つ目が追加)。
エインズワースによる愛着スタイルの分類
- 安定型(Secure Attachment):親と適度な距離を保ちつつ安心感を持つ
- 回避型(Avoidant Attachment):親への関心が薄く、依存を避ける
- 不安型(Anxious Attachment):親の注意を強く求め、不安定な行動を示す
- 恐れ・回避型(Fearful-Avoidant Attachment):親に対し愛着と恐怖が混在する。のちに追加された
そして、エインズワースの研究成果に基づいて、ハザンとシャイバー(1987)は成人の恋愛関係にも愛着スタイルが反映されることを以下のように示している。
- 安定型の人 → 信頼と親密さを自然に受け入れる
- 回避型の人 → 独立を重視し、距離を取る
- 不安型の人 → 過剰に相手を求め、不安になりやすい
なお、愛着スタイルは、生涯固定されるわけではなく、経験や努力によって変化させることが可能である点に注意が必要である。
私たちが浮気をなぜダメと感じるかは、愛着の安全性の観点から説明できる
理由②:本能的な忌避感
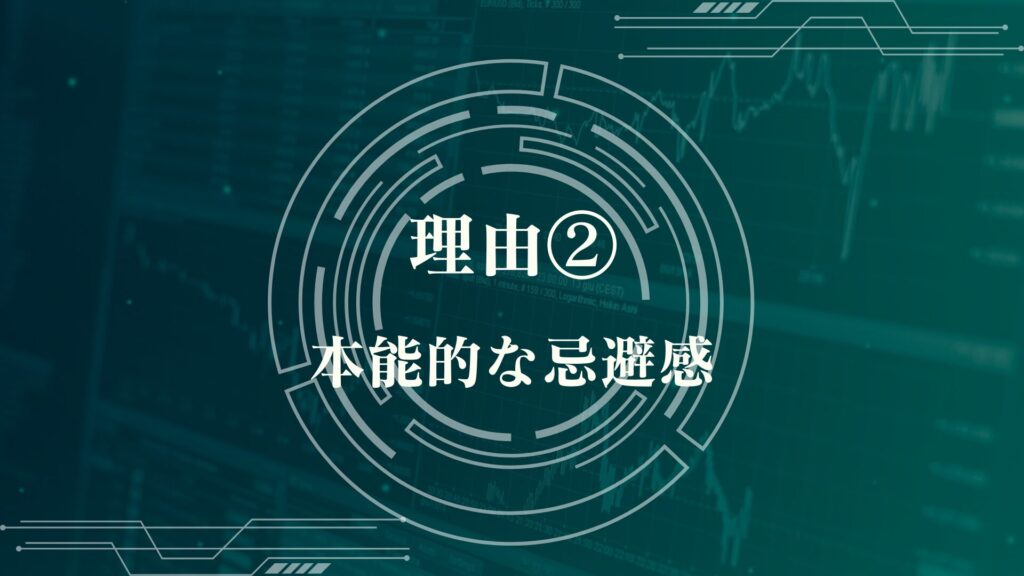
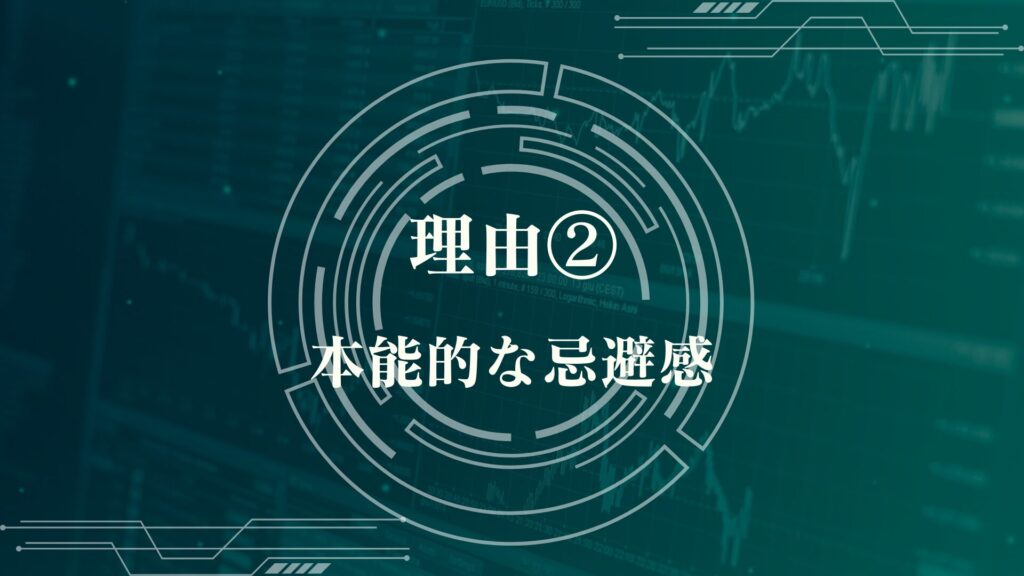
私たちが浮気をなぜダメと感じるかは、本能的な忌避感の観点から考えられます。
進化心理学によれば、人間の浮気に対する嫌悪感には、生存と子孫繁栄に関わる本能的な要素があるとされています。



生存と子孫繁栄に関わる本能的要素、、、んー、なんかめんどいね。
生存と子孫繁栄に関わる本能的な要素などというと、かなり大げさな感じがしますが、男女別にそれぞれ簡単に提示すると以下の通りです。
- 父性不確実性:男性は「自分の遺伝子を残せるか」を重視し、パートナーの浮気により「自分の子どもではない可能性」が生じる事を本能的に嫌がる
- 資源の分散リスク: 女性は進化的に「パートナーの資源を安定的に確保する事」が重要だったため、男性が他の女性に興味を持つと自分や子どもへの投資が減るリスクを感じ不安や怒りを覚える
私たちが浮気をなぜダメと感じるかは、本能的な忌避感の観点から説明できる
理由③:認知的不協和
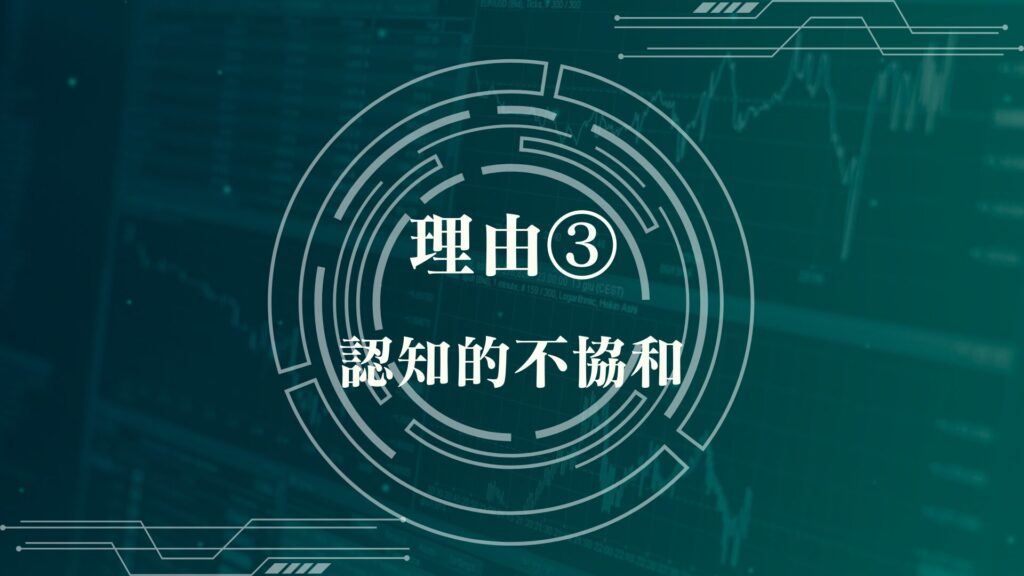
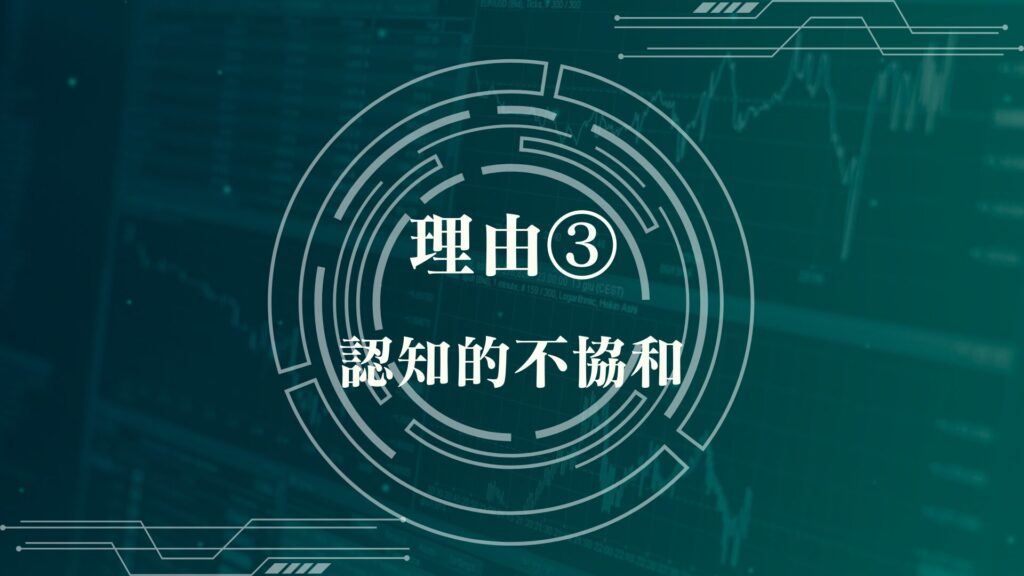
私たちが浮気をなぜダメと感じるかは、認知的不協和の観点から考えられます。
前述のように、人は本能的にパートナーの浮気を嫌がるわけですが、この忌避感はレオン・フェスティンガーの認知的不協和理論からも説明が可能です。



認知的不協和、、?
一般に、多くの人は恋愛関係では「相手に誠実であること」を前提とし、信頼関係を築く中で「自分は大切にされているはず」という認識が形成されていきます。
しかし、この認識等と矛盾する「浮気された事実」を知覚する事で、浮気された事実と既存の認識の間のギャップを解消したいという強いストレスが発生しそれが忌避感の根源となるのです。
「補足」レオン・フェスティンガーの認知的不協和理論とは?
認知的不協和理論(Cognitive Dissonance Theory)とは、レオン・フェスティンガー(Leon Festinger, 1957)により提唱された、「人は自分の信念・態度・行動の間に矛盾(不協和)が生じると、それを解消しようと心理的に調整する」という理論である。
人はそもそも「一貫性を保ちたいという欲求を持っている」ので、矛盾する2つの認知(考え・信念・行動など)を同時に持つと不快な緊張状態(不協和)が生じ、以下の3つの内のいずれか、ないし複数によってその解消を試みるとされる。
- 態度(考え方)を変える:(例:「喫煙は意外と害が少ないらしい」という情報を信じる)
- ② 行動を変える(例:「禁煙しよう」と決意し、タバコをやめる)
- ③ 新しい認知を追加する(例:「ストレスを減らすためには喫煙も必要」と正当化する)
この認知的不協和を恋愛の文脈で考えると、恋人に浮気されたが関係を続ける人の心理的背景には、「浮気されたのは嫌だがわかれるのもつらい」という不協和状態を解消するために、「でも彼(彼女)は本当は優しいし、今回は仕方なかった」などといった正当化があったと解することができる。
私たちが浮気をなぜダメと感じるかは、認知的不協和の観点から説明できる
理由④:自己肯定感とアイデンティティの喪失
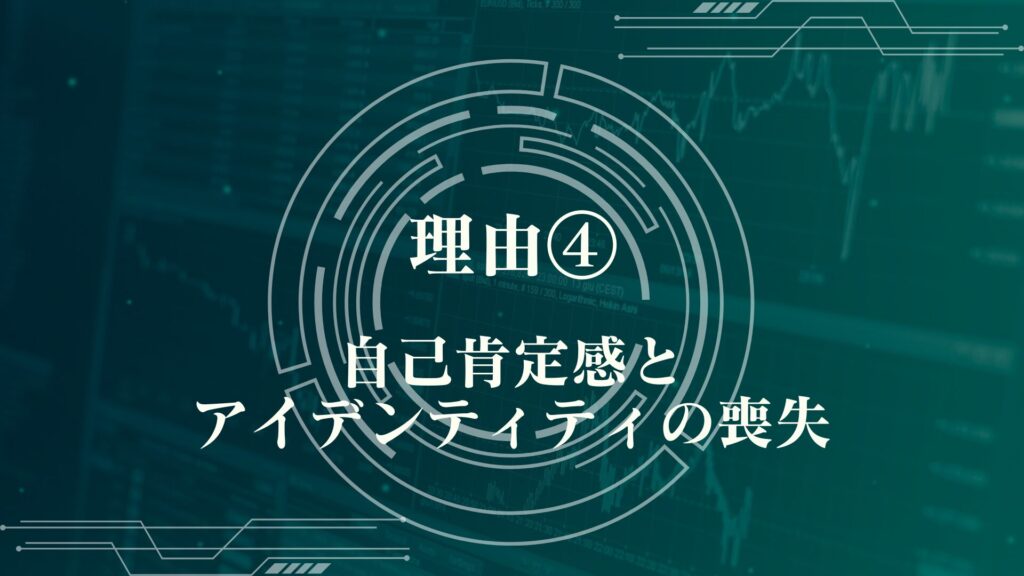
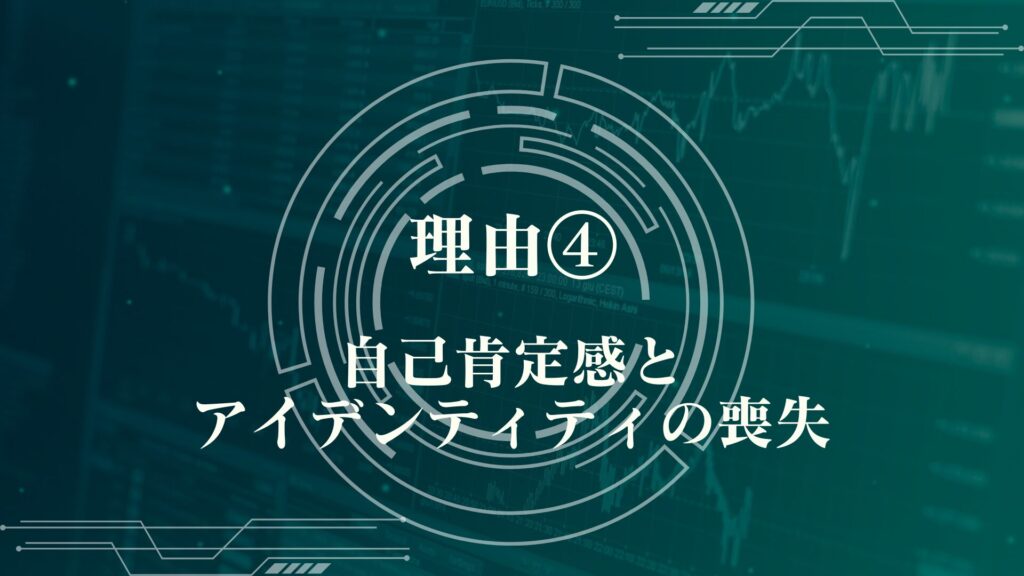
私たちが浮気をなぜダメと感じるかは、自己肯定感とアイデンティティの喪失の観点から考えられます。
前述のように、浮気によってアイデンティティの一部が欠損するので、浮気された方はかなり手痛い精神的ダメージをこうむるものです。



信頼していた所を裏切られるわけだからね、、、きついよね。
このアイデンティの欠損によって、「自分は愛される価値がないのでは?」という疑念が生じたり、「自分より魅力的な人がいたのか?」という比較が生じ自己肯定感が低下する可能性があります。
自己肯定感が低下すると、ますます浮気されやすくなってしまうので、まさに悪循環といわざるをえません。経験上そのことを知る人が多くいるため、浮気をされたくないと思うのは自然なことでしょう。
私たちが浮気をなぜダメと感じるかは、自己肯定感とアイデンティティの喪失の観点から説明できる
浮気がなぜダメかわからない人の思考を変える4つのアプローチ





浮気がなぜダメかわからない人の思考は、変えられる?



以下の4つのアプローチを、試してみよう!
ここまで、浮気がなぜダメか等についていろいろとみてきたので、次は浮気がなぜダメかわからない人の思考を変えるにはどうしたらいいかについて考えてみたい思います。
浮気がなぜダメかわからない人の思考を変えるアプローチは、以下の通りです。
浮気がなぜダメかわからない人の思考を変える4つのアプローチ
- アプローチ①:認知行動療法(CBT)の活用
- アプローチ②:パートナーの感情や視点 の共有
- アプローチ③:環境の見直し
- アプローチ④:倫理観と価値観の再評価



それぞれ、詳しく見ていこう!
アプローチ①:認知行動療法(CBT)の活用


浮気がなぜダメかわからない人の思考を変えるためには、認知行動療法(CBT)を活用するアプローチが有効かもしれません。
認知行動療法とは非常に簡単に言えば、認知と行動を変える事によって思考パターンや行動を修正していこうという心理療法の事です。性犯罪の再発防止プログラムにおいても、認知行動療法は用いられており効果が上がっています。



なるほど、、認知と行動を変えるかあ、、。
また、認知行動療法の手法を浮気の防止に活用している人々は世の中にたくさんおり、一定の成果を上げているようです。
もしパートナーの浮気リスクが高そうに感じるのであれば、一度、浮気防止に特化したカウンセラーなどに依頼してパートナーにカウンセリングを受けてもらうといいでしょう。
「補足」認知行動療法とは?
認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy, CBT)は、思考(認知)・感情・行動の関係に注目し、問題となる思考や行動パターンを修正することで、心の健康を改善する心理療法の一つである。
認知行動療法の基本的な考え方には、以下の3つある。
認知行動療法の基本的な考え方
- 認知(思考)が感情や行動に影響を与える
- 非合理的な思考や認知のゆがみが、心理的な問題を引き起こす
- 認知(思考)を柔軟に修正し、適応的な行動をとることで、感情の改善を目指す
なお、認知行動療法で用いられる手法の例としては、以下のようなものがある。
認知行動療法で用いられる手法の例
- 認知再構成(リフレーミング):ネガティブな思考パターンを特定し、より適応的な考え方に置き換える。
- 行動活性化:落ち込みや無気力の際に意識的に活動を増やし、ポジティブな経験を積む
- エクスポージャー(曝露療法):不安や恐怖の対象に段階的に慣れることで、回避行動を減らし適応的な行動を促す
- 行動実験:例(「人前で話すと必ず笑われる」といった思い込みが本当かどうか、実際に試して検証する)
- マインドフルネス:今この瞬間に意識を向け、判断をせずに受け入れることで、ストレスを軽減する。
なお、認知行動療法を浮気治療に適用する場合は、浮気の背景にある思考や行動パターンを見直して、より健全な関係を築くためのスキルを身につけるような方向性で行われる。
認知行動療法の活用は、浮気がなぜダメかわからない人の思考を変えるために有用
アプローチ②:パートナーの感情や視点 の共有
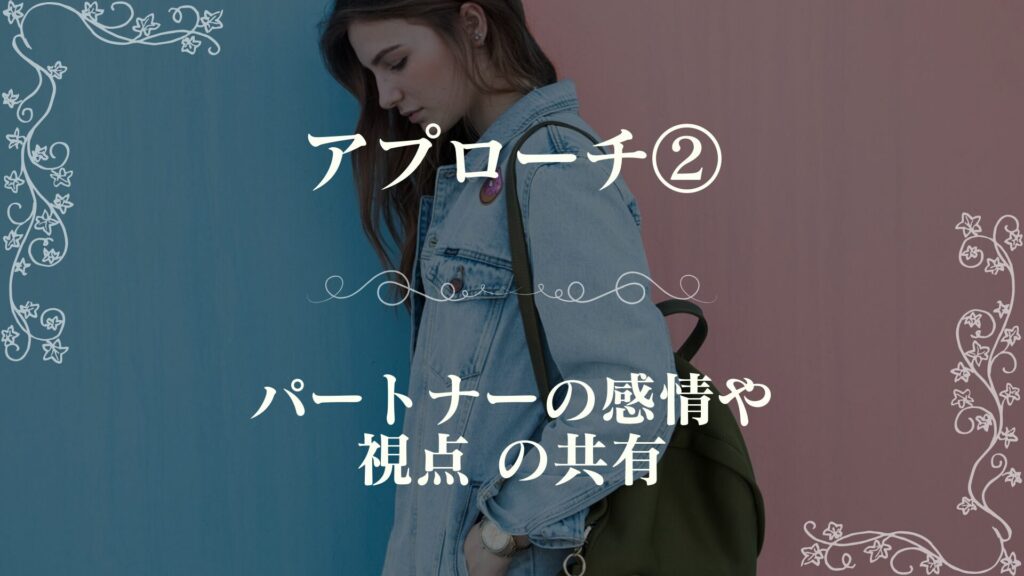
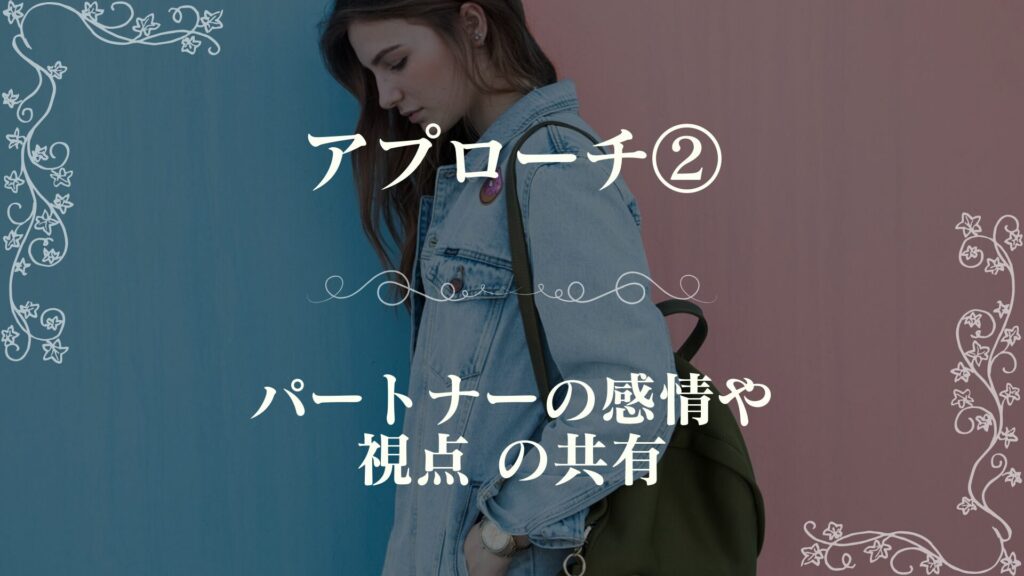
浮気がなぜダメかわからない人の思考を変えるためには、パートナーの感情や視点 の共有する事が有効かもしれません。
パートナーの感情や視点 の共有し理解する事で、多くの場合は浮気が相手に与える痛みや信頼の損失を実感でき、それが浮気への抑止力として働くようになります。



ふむ、まるほどね。
さらに言うと、共感能力を高めるトレーニングやワークショップに参加することで、他者の感情に対する敏感さが養われて浮気の抑止が促進される可能性が高まるでしょう。
ただし、こう言ったアプローチは、大前提として共感性やそれに基づく罪悪感がわずかでもある場合にしか基本的には、有効ではない点に注意が必要です。そのため、いわゆるサイコパスなどには、何らの効果も期待できないでしょう。
パートナーの感情や視点 の共有は、浮気がなぜダメかわからない人の思考を変えるために有用
アプローチ③:環境の見直し


浮気がなぜダメかわからない人の思考を変えるためには、環境の見直しが有効かもしれません。
人は、良くも悪くも環境の影響を強く受けてしまうものなので、例えば、これまでまったく浮気をしたことがない人であっても、浮気が蔓延する職場に身を置けば自身も浮気を肯定するようになってしまう可能性があります。



ええ、、、そ、そうなの?ヤバいね、、、環境って、、。
同じような事は、浮気がなぜダメかわかっていない人にとっても言えるので、もしパートナーが浮気がなぜダメかわかっていなかった場合は、環境の調整などによって浮気に対する態度が変容する可能性があります。
なお、浮気が蔓延する職場環境に身を置いていたり浮気が常習化した友人知人が多い場合には、かなり浮気リスクが高まるので、中々一筋縄ではいきませんが率先して対処するのが望ましいでしょう。
環境の見直しは、浮気がなぜダメかわからない人の思考を変えるために有用
アプローチ④:倫理観と価値観の再評価


浮気がなぜダメかわからない人の思考を変えるためには、倫理観と価値観の再評価が有効かもしれません。
浮気がなぜダメかわからない人は、これまでの生育環境や身を置いてきた環境などによって、浮気が悪いとは思わなくなってしまった可能性が高いです。



ふむ、そうね、親が不倫三昧だったりとかだとゆがみそうよね。
そのため、本人に自身の倫理観や価値観を見直してもらって、浮気が自分や周囲に与える影響を内省してもらうのが有効でしょう。ただ、自分だけで内省して改善するのは、浮気に対して多少なりとも罪悪感がある人やよほどメタ認知の高い人くらいの者でしょう。
そのため、万全を尽くすという意味では、専門家や専門機関に倫理的な教育やカウンセリングを行ってもらって、浮気の道徳的側面を理解してもらったり行動を制御するスキルの習得を頑張ってもらう方がいいでしょう。
倫理観と価値観の再評価は、浮気がなぜダメかわからない人の思考を変えるために有用
浮気はなぜダメかに関連するFAQ





浮気はなぜダメかに関連して、気になることが、、、。



最後に、浮気はなぜダメかに関連する疑問に関して、答えていきましょう。
浮気はなぜダメかに関連するFAQ①:パートナーの浮気が発覚したらどうしたらいい?
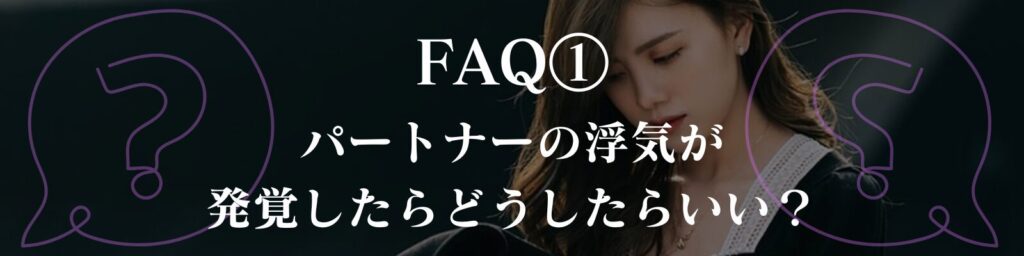
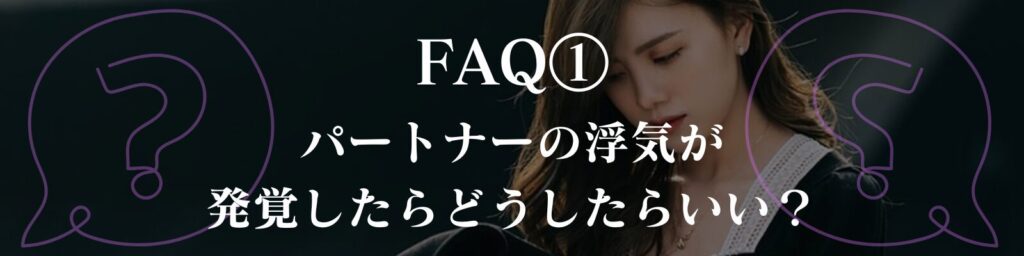
パートナーの浮気が発覚したら、まずは冷静に状況を把握することから始めるのが重要です。間違っても、感情的にパートナーに詰め寄るようなことをしないようにしましょう。
パートナーの浮気が発覚した際の対応について、詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてみてくださいね。
浮気はなぜダメかに関連するFAQ②:浮気しない男性はいる?
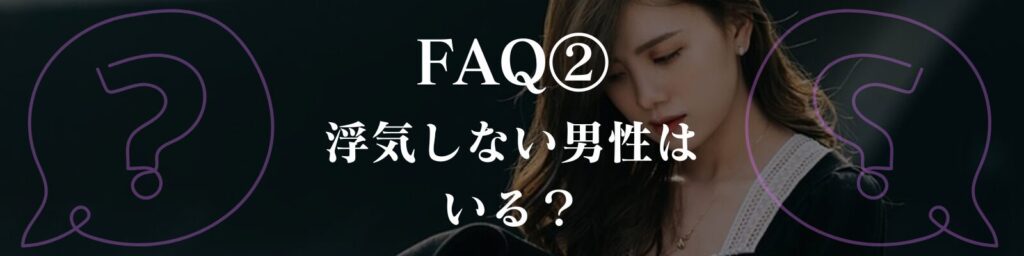
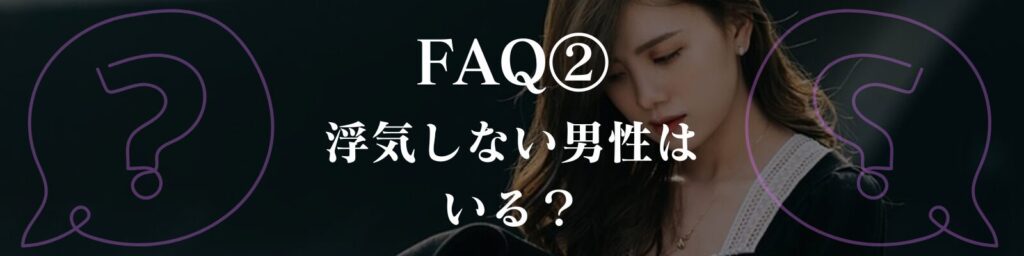
浮気をしない男性はいない等といわれることがありますが、現実には、浮気をしない男性もいます。そのような男性の特徴の最たるものは、貞操観念が非常に高いというものでしょう。
浮気をしない男性の特徴について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を見てみて下さい。
参考
浮気はなぜダメかに関連するFAQ③:浮気されやすい人の特徴とは?
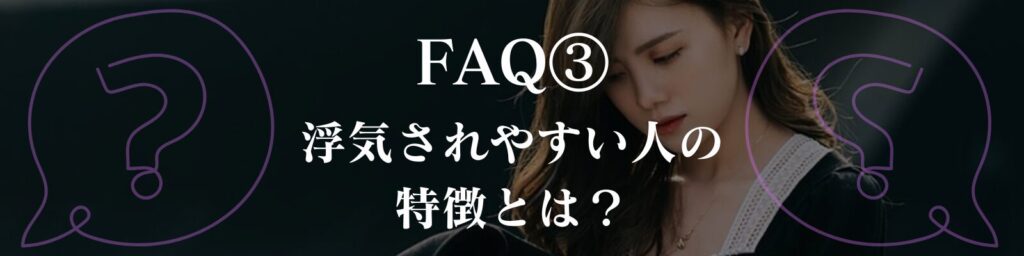
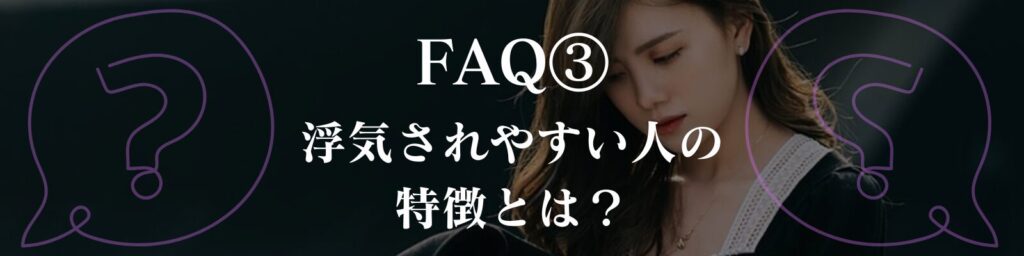
浮気されやすい男女は、パートナーに尽くしすぎるという傾向にあります。また、自己肯定感が低い事も、浮気をされやすい方に共通していりますね。特に男性の場合、自己肯定感の低さは浮気される確率がかなり高くなってしまいます。
浮気されやすい人について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事へどうぞ。
参考
浮気はなぜダメかに関連するFAQ④:浮気を気にしない人はいる?
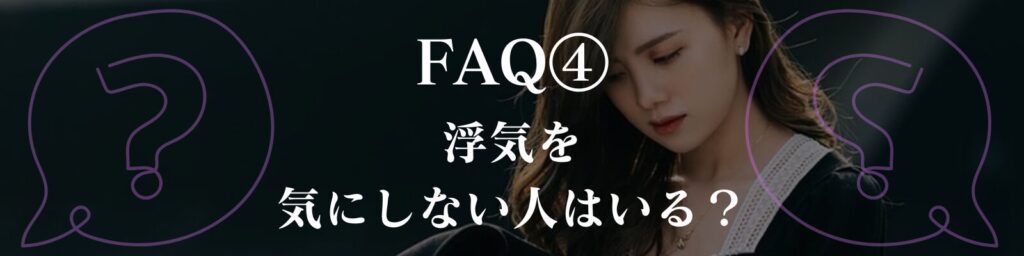
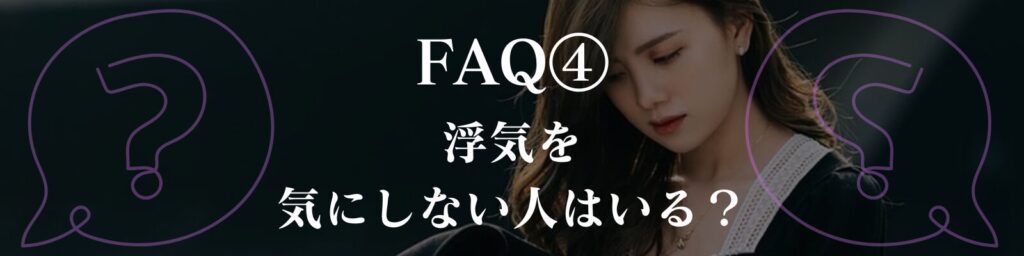
浮気によって、傷つかない人はいません。ただその傷つき度合いや立ち直りの速さには、かなりの個人差があります。
そのため、中には浮気をされても大して気にしない、もしくは割り切っているがゆえに、パートナーに浮気されても動じないという人達も少数ながら存在しています。
浮気されても気にしない人の心理について、詳しく知りたい方は以下の記事を見てみてくださいね。
参考
浮気はなぜダメかに関連するFAQ⑤:浮気・不倫しやすい人特有の顔の特徴はある?
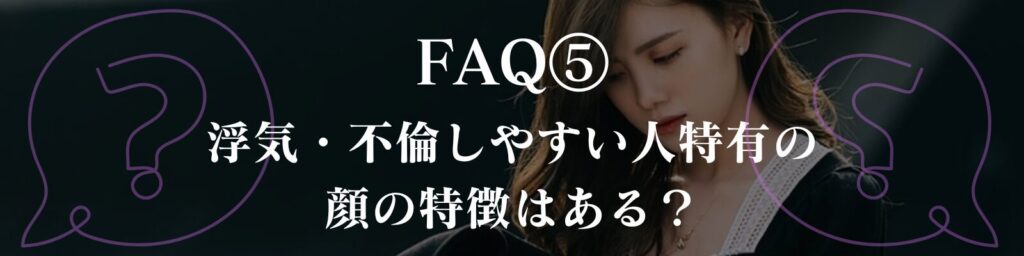
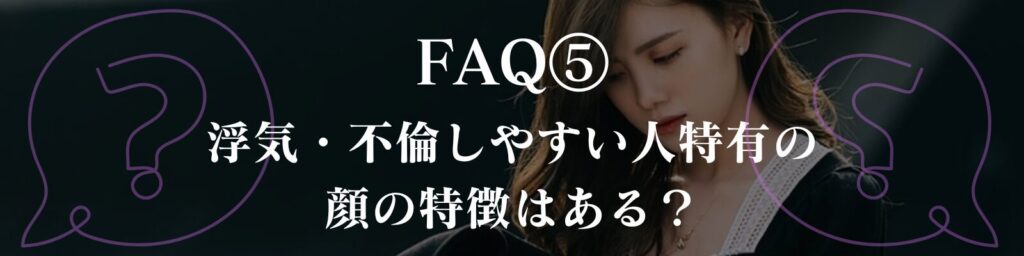
浮気・不倫しやすい人顔には、特有の特徴があるといわれることがままあります。例えば、ある研究によれば、男性の場合は幅広で男性的な顔であるほど浮気しやすい傾向にあるとのことです。
また、女性の場合、人相学における女郎相と呼ばれる顔つきをした女性の浮気リスクが高い傾向にあるといわれることがあります。男女の浮気顔の特徴について詳しく知りたい方は、それぞれ以下の記事を見てみて下さいね。
参考
浮気はなぜダメかに関連するFAQ⑥:美人ほど浮気されてない?
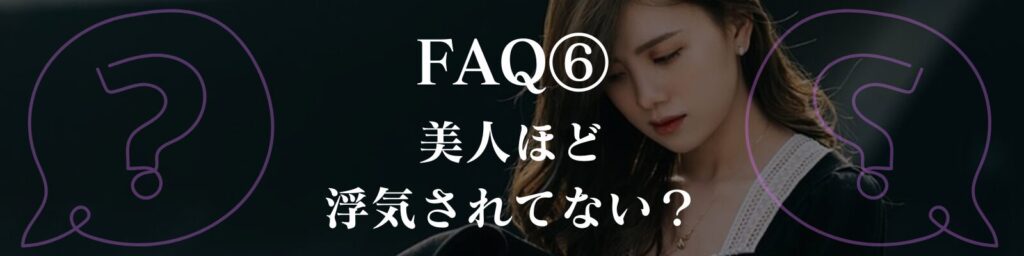
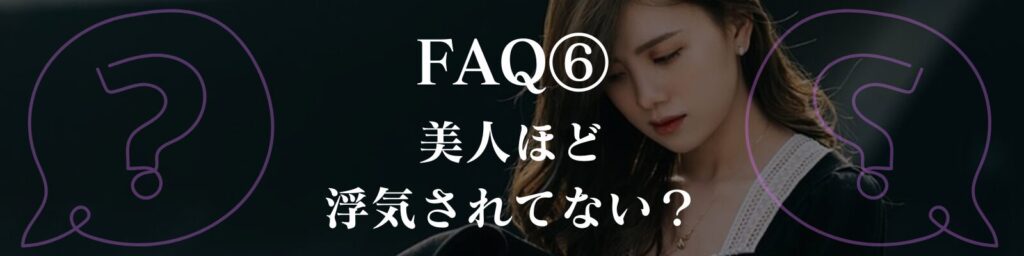
美人ほど浮気されているという俗説は、まま聞かれます。ただ、この俗説に関する明確なエビデンスはありませんので、確かなことは何も言えません。ただ、私の体感では、美人ほど不幸な恋愛をしているように感じます。
その元凶の内で個人的に有力と思うものは、美人ほど浮気やDV上等のいわゆるクズの男性と付き合ったり結婚している事です。美人の浮気リスク等に関して詳しくは、以下の記事をご覧ください。
浮気はなぜダメかに関連するFAQ⑦:浮気の多い年齢は何歳くらい?
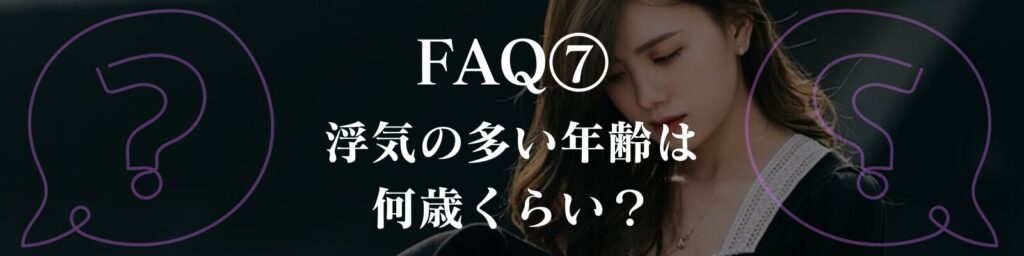
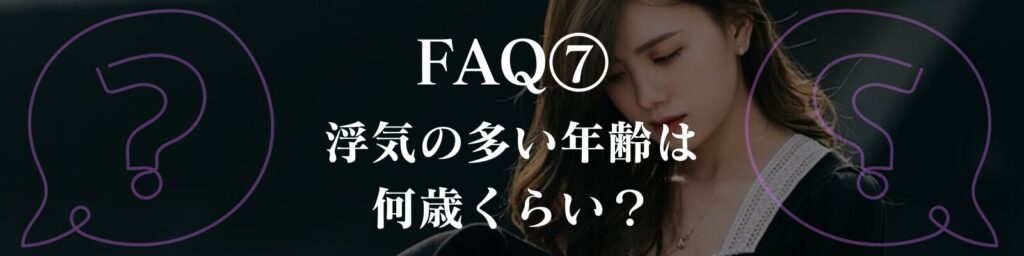
浮気の多い年齢は、男女ともに大体20代後半~~30代前半頃といわれています。ただ、男女で多少の違いはあるようです。
浮気の多い年齢について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事からどうぞ。
浮気はなぜダメかに関連するFAQ⑧:朝帰りの言い訳にはどう対処したらいい?
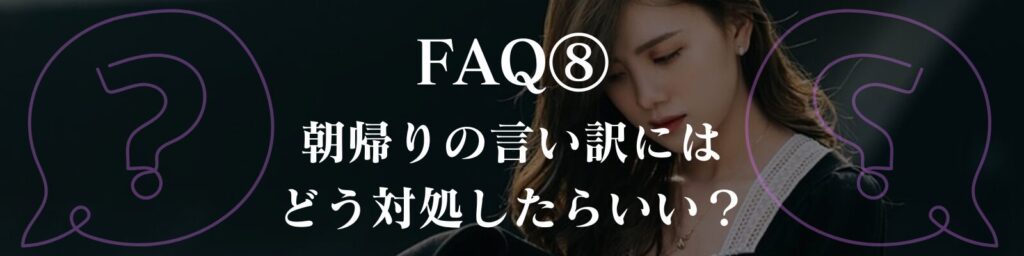
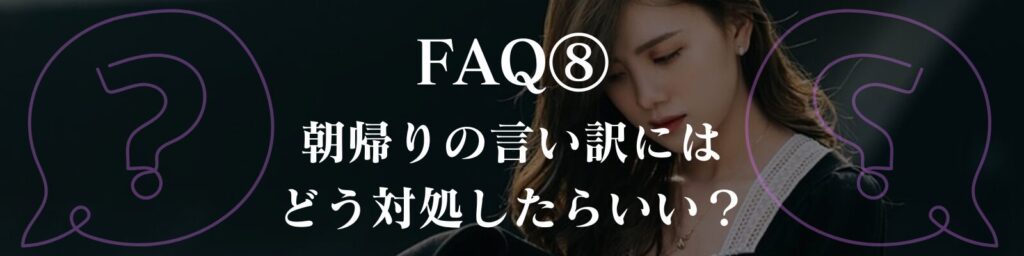
パートナーが朝帰りの際に発する言い訳に対しては、まず冷静にパートナーの言い分を聞いて状況を整理することが大事です。感情に任せて問い詰めても、何もいい事はありません。
パートナーの朝帰りの言い訳に対する対処に関して、さらに詳しく知りたい方は以下の記事を見てみてください。
浮気はなぜダメかに関連するFAQ⑨:同窓会での浮気確率はどれくらいなの?
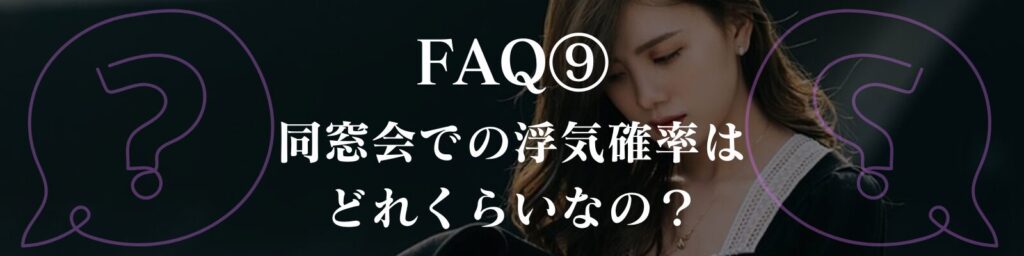
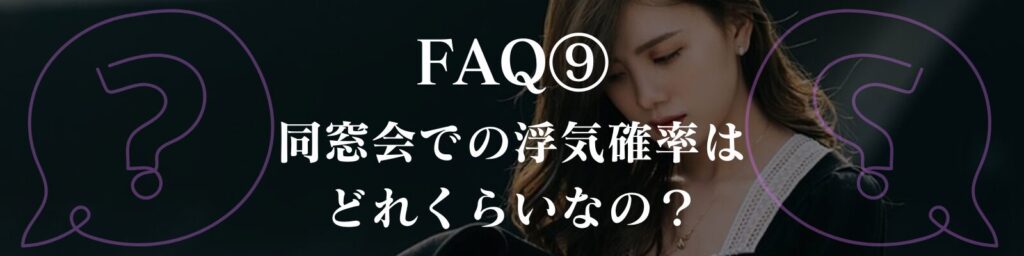
同窓会での浮気確率は、あるデータによれば約9%程度と考えられます。
同窓会での浮気確率についてさらに詳しく知りたい、またはや浮気確率を下げるための方法について知りたい方は以下の記事へどうぞ。
浮気はなぜダメかに関連するFAQ⑩:どこからどこまでが浮気なの?
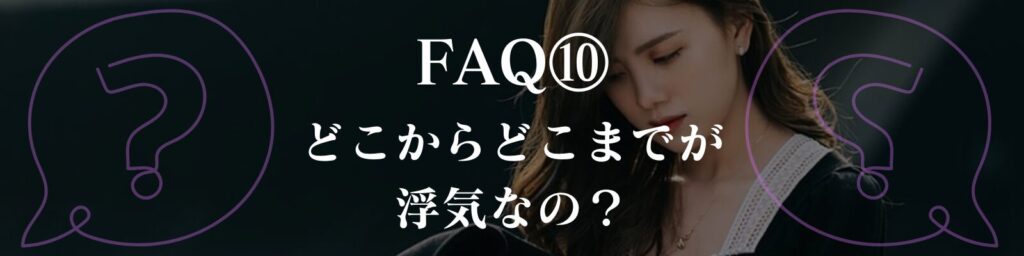
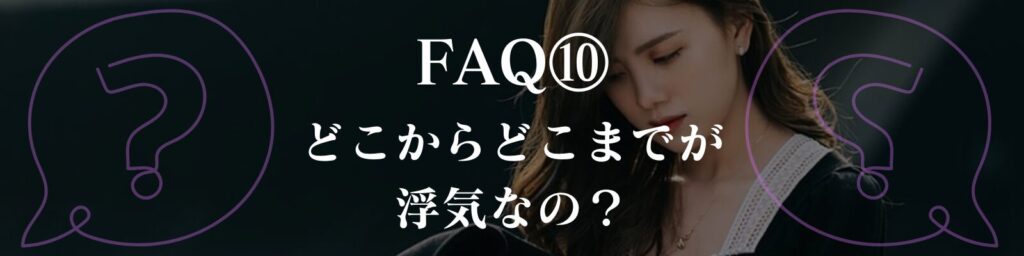
どこからを浮気とするかについては、男女でかなり違いがありますが、一般的には女性の方が浮気認定の幅が男性よりも広い傾向にあります。
どこからを浮気するとするかについて詳しく知りたい方は、以下の記事を読んでみてくださいね。
浮気がなぜダメかは社会、生物、心理の3つの視点からそれぞれ説明可能!浮気疑惑がある時は早めに真相を突き止めよう!


浮気がなぜダメかは、社会、生物、心理の3つの視点からそれぞれ説明可能ですが、一番説得力のあるものは社会的視点からみた「社会秩序等の維持のため」という理由でしょう。ただ、個人レベルで考えると、心理的ダメージなどの影響が一番問題です。
そして、パートナーに浮気疑惑がある場合は、早めにその真相を明らかにし今後の対応をきめるのが最善です。ただ自分で調査してはバレる可能性が高いため、安全かつ確実にの真相を突き止めたいなら優秀な探偵社に依頼するのがベストですね。
もちろん、調査をせずとも相談して調査が必要なのかを、判断するのもいいと思います。さあ、今こそパートナーの浮気の真相を突き止め、その後の対策をスムーズに進めるために行動を起こしましょう!
╲提携探偵社はえりすぐりの全国100社以上╱
╱相談・面談・紹介は無料╲
